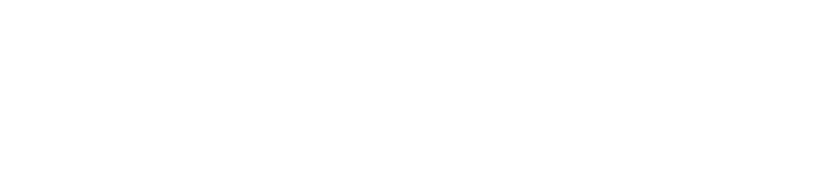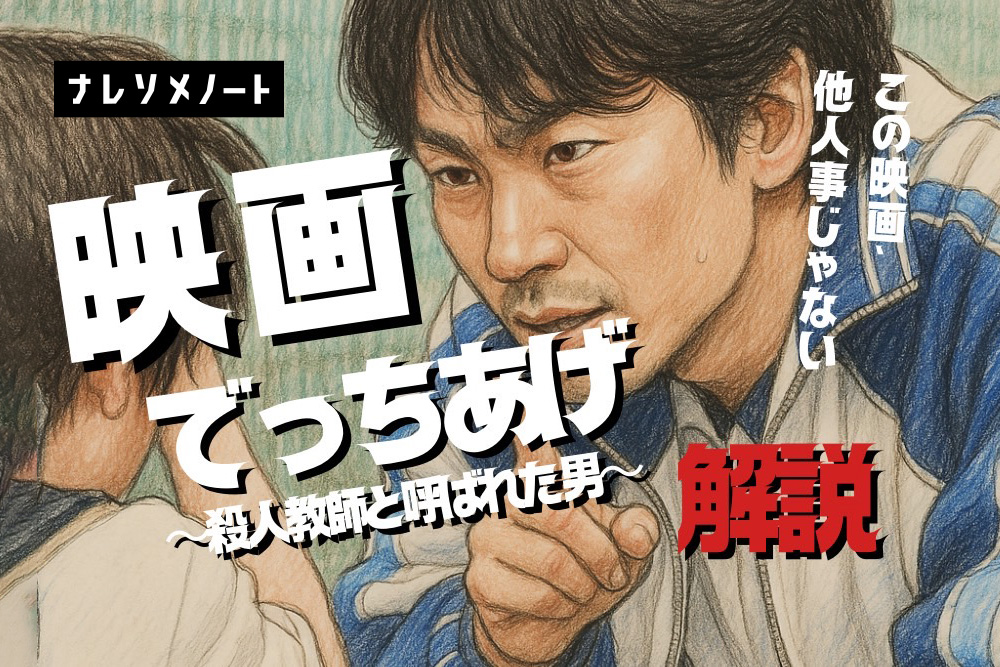「スペック」で、結婚できる確率はここまで変わる。ある論文が解き明かした婚活のリアル
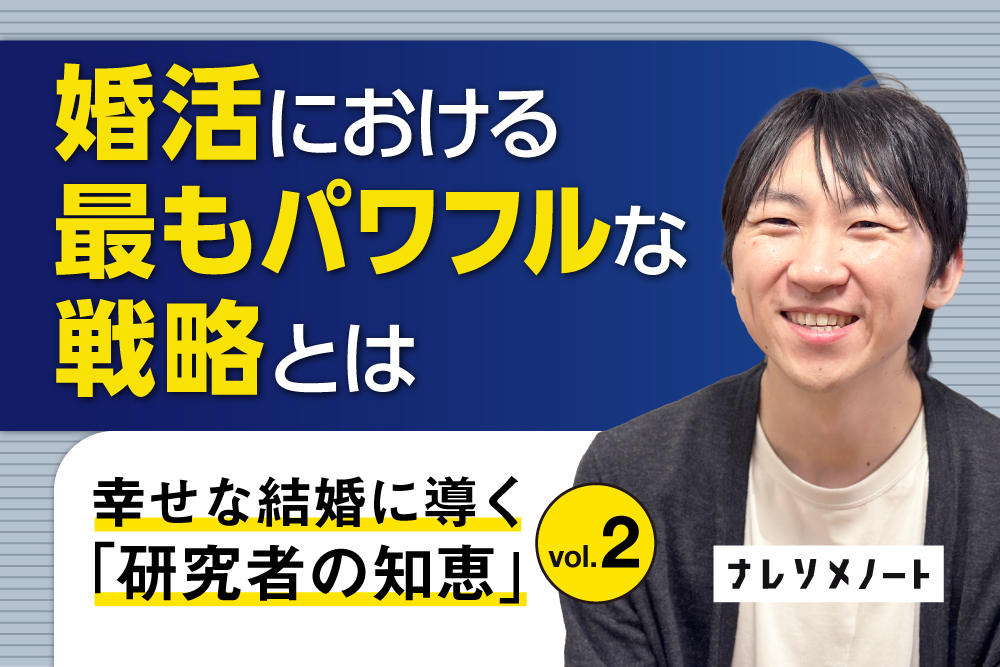
「婚活」という言葉が社会に定着して久しい現代。生涯未婚率が上昇を続ける一方で、多くの人が結婚を望み、そのための活動に励んでいます。
では、その婚活の場で、最終的に結婚というゴールにたどり着ける人とそうでない人を分けるものは、一体なんでしょうか。
努力で乗り越えられる壁なのでしょうか、それとも、もっと変えがたい要因が影響しているのでしょうか。
2016年に発表された小林盾氏と能智千恵子氏による論文『婚活における結婚の規定要因はなにか』は、この根源的な問いに、大規模な量的データを用いて正面から向き合った画期的な研究です。
これまで個人の体験談や事例分析が中心だった婚活研究の分野に、「全体の傾向」という客観的な視点をもたらしたこの論文は、婚活の現実を浮き彫りにし、結婚を望むすべての人に重要な示唆を与えるでしょう。
本稿では、この論文の内容を詳しくレビューし、その衝撃的な結論と、私たちがそこからなにを学び、どう行動すべきかを考察します。
研究の舞台裏:データが語る婚活のリアル
この研究の特筆すべき点は、その分析の土台となったデータの独自性にあります。
著者らが分析対象としたのは、愛媛県の事業である「えひめ結婚支援センター」のお見合い事業に登録した全会員、実に4,779人分のデータです。これは、特定の個人の成功譚や失敗談ではなく、約4年間にわたる数千人規模の活動記録に基づいた、極めて客観性の高いデータと言えます。
分析手法には「イベント・ヒストリー分析」という統計モデルが用いられています。これは、ある出来事(この場合は「結婚による退会」)が起こるまでの期間と、それに影響を与える要因を分析する手法です。現時点で結婚していない人も「まだ結婚していないだけで、今後する可能性がある」として分析に含めることができるため、婚活のような長期的なプロセスを解明するのに非常に適しています。
分析のゴールは、「結婚による退会」のしやすさ(ハザード率)とされました。これには、センターのお見合い事業で結婚が決まったケースだけでなく、センター外で結婚が決まったり、恋人ができて退会したりするケースも含まれています。
そして、このゴールに影響を与える要因として、年齢、身長、学歴、雇用形態、収入、結婚経験の有無といった個人の属性が投入され、なにが結婚のチャンスを高め、なにが妨げるのかが分析されました。
衝撃の分析結果:男女で全く異なる「結婚のルール」
分析によって明らかになったのは、婚活市場における成功のルールが、男性と女性で劇的に異なるという事実でした。
【男性】年収100万円増で結婚のチャンスは1.13倍上昇。結婚に影響を与える「社会経済的地位」
男性の場合、結婚のチャンスを左右する最大の要因は、教育、雇用、収入といった「社会経済的地位」でした。具体的には、以下の点が統計的に有意な促進要因として示されました。
- 高い教育レベル:論文では教育年数4年(例えば高卒から大卒へ)で結婚のチャンスが1.38倍に上昇すると示されています。
- 正規雇用:非正規雇用の人に比べて、正規雇用の男性は結婚のチャンスが1.73倍も高くなりました。
- 高い収入:個人年収が100万円増えるごとに、結婚のチャンスは1.13倍に上昇しました。
かつてバブル時代に言われた「三高(高身長・高学歴・高収入)」という言葉がありましたが、この研究結果は、現代の婚活においても、身長、学歴、収入が高い男性ほど有利であるという現実を裏付けています。
特に、学歴と収入は本人の努力や能力を反映する部分もありますが、正規雇用であるかどうかという「働き方」が、これほどまでに結婚の可能性を左右するという事実は、現代社会の構造的な問題を浮き彫りにしているとも言えるでしょう。
これらに加え、身長が高いこと(10cm高くなるごとにチャンスが1.25倍)、そして年齢が若いこと(10歳年をとるとチャンスが0.63倍に減少)も、結婚を促進する重要な要因でした。
男性の婚活は、まさに個人の持つ「スペック」が厳しく評価される場であることが、データによって示されたのです。

※画像はイメージです
【女性】10歳年をとると、結婚のチャンスは0.55倍。鍵を握るのは「年齢」
一方で、女性の結果は男性とは対照的でした。驚くべきことに、女性の場合、学歴、雇用形態、収入といった社会経済的地位は、結婚のしやすさに統計的な影響を与えませんでした。つまり、女性が高い学歴を持っていようと、正規雇用で働いていようと、高収入であろうと、それが直接結婚のチャンスを高めることにはつながっていなかったのです。
では、女性にとってなにが決定的な要因だったのでしょうか。分析が示した答えは、非常にシンプルでした。
- 年齢が若いこと:10歳年をとると、結婚のチャンスは0.55倍へと大きく減少しました。これは男性の減少率(0.63倍)よりもさらに厳しい数値です。
- 結婚経験があること:後述しますが、結婚経験のある女性は、ない女性に比べてチャンスが2.06倍に上昇しました。
つまり、女性の婚活においては、本人のキャリアや経済力といった「スペック」よりも、若さという側面が、結婚の可能性を規定する圧倒的な要因となっていたのです。
この結果は、女性の価値が依然として若さに重きを置いて評価されがちな、社会の根強い価値観を反映しているのかもしれません。
「婚姻歴」が結婚の確率を高める
社会経済的地位の効果が男女で非対称であった一方、両性に共通して結婚を強力に後押しする要因がありました。それは「婚姻歴があること」です。
分析によれば、婚姻歴のある人は、ない人と比べて、男性で1.77倍、女性では2.06倍も結婚のチャンスが高まりました。これは一見すると意外に感じられるかもしれません。
しかし論文では、人的資本論の観点からこの結果を説明しています。一度結婚生活を経験した人は、家事や円滑なコミュニケーションといった「結婚生活を送るためのスキル」を既に身につけていると見なされる可能性があります。
そのため、相手から「この人となら安定した結婚生活が送れそうだ」という期待を持たれやすく、結果として結婚に結びつきやすいのではないか、と考察されています。
論文が示す、最も確実でパワフルな婚活戦略
さて、ここまで見てきた分析結果は、人によっては非常に厳しい現実に感じられるかもしれません。身長や学歴、正規雇用の地位など、今から変えるのが難しい要因が結婚を左右するからです。
では、私たちはこの現実を前に、ただ手をこまねいているしかないのでしょうか。
この論文の最大の功績は、この厳しい現実を提示するだけでなく、そこから導き出される極めて実践的で、誰にでもコントロール可能な戦略を示したことにあります。それは、「婚活を1年でも、1日でも早くスタートさせること」です。
論文が明らかにしたように、年齢は男女ともに結婚を左右する最も強力な要因の1つです。そして、他のスペックとは異なり、「婚活を始める年齢」は、完全に個人の意思決定に委ねられています。
著者らは、この「コントロール可能性」こそが重要だと指摘します。

※画像はイメージです
例えば、非正規雇用の男性は、正規雇用の男性に比べて結婚のチャンスが約半分(0.58倍)になってしまいます。しかし、もし彼が婚活を10年早くスタートさせていれば、その年齢効果(不利を1.6倍近く覆す効果)によって、雇用の不利をほぼ相殺できる可能性があるのです。
また女性の場合も、1日でも早く婚活をすることでパートナーと結ばれる可能性が高まります。さらに、仮にそのパートナーと離婚しても、次のパートナーと結ばれやすくなることが調査結果から明らかです。
すると、仮に5年先を見据えた場合、「離婚歴がある状態」と「独身のままでいる状態」なら、前者のほうが結婚の可能性を高められます。もちろん、最初に結ばれたパートナーと幸せな家庭を築けるのがベストですが、仮に失敗しても、再チャレンジがしやすいのです。
この事実は、婚活に対する私たちの意識を根本から変えることになるでしょう。これまで婚活は、「自然な出会いがなかった場合の最終手段」と見なされる風潮がありました。しかし、この研究結果は、むしろ逆の発想を提案します。結婚を少しでも意識しているならば、相手がいるいないにかかわらず、できるだけ早期に活動を開始することこそが、最も合理的で効果的な戦略である、と。
論文によれば、この調査における婚活のスタート平均年齢は男性41.4歳、女性37.0歳でした。もし、これを10年早め、男性が30代、女性が20代でスタートできていたなら、結婚に至る可能性は男性で1.6倍、女性で1.8倍以上も高まっていた計算になります。
厳しい現実の先にある、主体的な選択
小林・能智両氏によるこの論文は、「婚活の成功は個人の魅力や努力次第」といった曖昧な精神論に、冷徹なデータを突きつけました。男性は社会経済的地位という「スペック」が、女性は「年齢」が結婚を規定するという現実は、多くの人にとって受け入れがたいものかもしれません。
しかし、この研究は絶望を語るのではありません。むしろ、客観的なデータによって「戦場の地図」を明確に示したことで、私たち1人1人が、より現実的で効果的な戦略を立てることを可能にしてくれます。
変えられない条件を嘆くのではなく、自らがコントロール可能な最大の変数である「時間」をどう使うか。この論文は、現代の結婚をめぐる厳しい現実を描き出すと同時に、その中でいかに主体的に未来を切り開いていくべきかという、力強いメッセージを私たちに投げかけているのです。結婚を望むすべての人にとって、一読の価値がある研究と言えるでしょう。
【所長・山崎の考察】スペック重視の背景にある「結婚観の変化」
結婚相談所での婚活に関するビッグデータが示すのは、女性の年齢、また男性の年齢、年収、身長、学歴、及び正規雇用が結婚チャンスを大きく左右するという事実です。これらは個々人の性格や結婚への熱意が結婚チャンスに与える影響を否定するものではありません。
一方で、結婚相談所において若さや高収入が結婚チャンスを高める要因であることは、紛れも無い事実といえます。結婚意欲が高く、年齢や年収、学歴などの情報開示をいとわない男女がマッチングする結婚相談所のシステムだからこそ、これらの社会経済的要因が重視されていると考えられます。
近年、結婚相談所やお見合いを利用した婚活、いわゆる見合い婚が増加傾向にあります。2010〜2014年に5.3%、2015-2018年に6.1%だった見合い婚の割合は、2019-2021年に9.8%まで増加(国立社会保障・人口問題研究所,2023)しています。なお、同時期に、年齢差が大きい男女の結婚の割合が減少し、1歳差または同年齢の男女の結婚の割合が増加しています。つまり、見合い婚の増加と同時に、近い年齢でのマッチングが増加していると言えます。
いわゆる「適齢期に出会った相手と、なんとなく(流れで)結婚する」というマッチングが減少し、「自分の市場価値やライフビジョン、結婚観に沿った相手を選んで結婚する」という流れが浸透しつつあると考えられます。
よって、今回レビューした論文で分析されたデータは2016年以前のものであり、現代においては結婚チャンスと社会経済的要因との関連がより強まっているかもしれません。
引用:国立社会保障・人口問題研究所(2023). 『現代日本の結婚と出産―第16回出生動向基本調査(独身者調査ならびに夫婦調査)報告書』