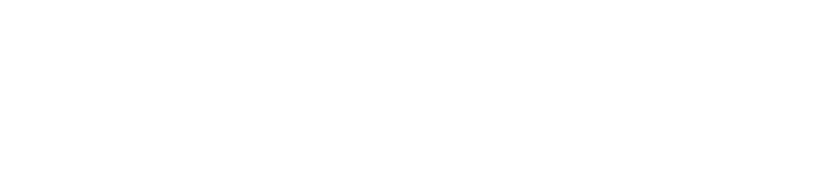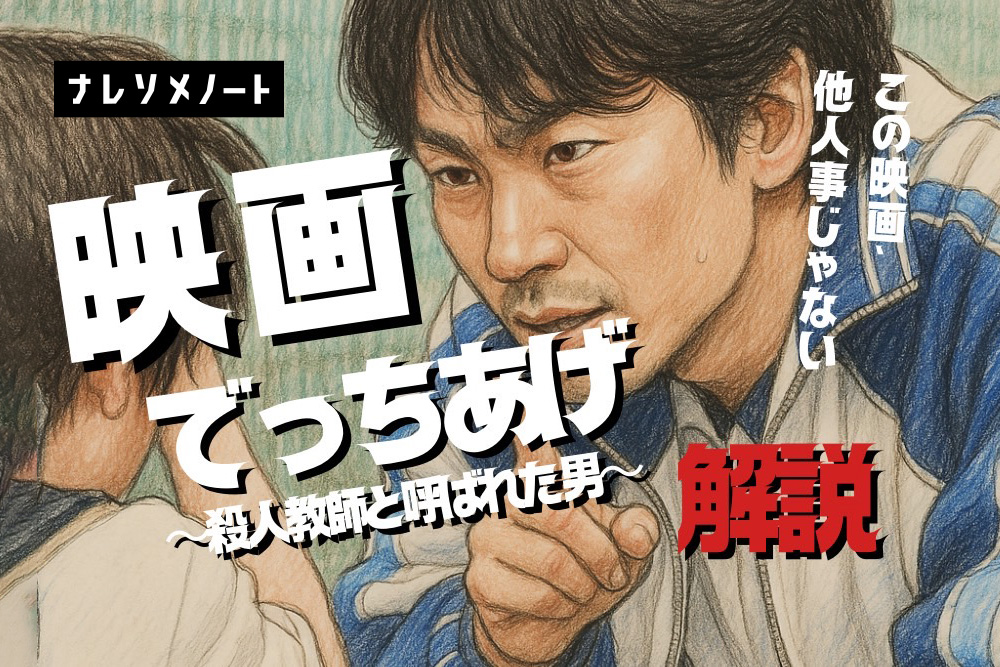相手の年収だけで結婚すると後悔する。4000組の家計を見てわかった、婚活時に見るべき本当の『価値観』とは?

ただ「好き」という感情だけでは、この先の長い人生を共にするパートナーシップは築けない。
そう考えるあなたにとって「結婚」は、まるで2人が共同創業者となる起業のようなものかもしれません。
その事業を成功に導くには、ビジョン(将来像)と事業計画(お金の計画)の共有が不可欠です。しかし、その本質的な対話を、どのように進めればいいのか──。合理的に考えたいからこそ、感情的なすれ違いで時間を無駄にしたくない、と感じる方も多いでしょう。
そこで、今回は前後編の2回にわたり、お金について「パートナーと建設的な対話」を進めるためのヒントを探ります。
お話を伺ったのは、これまで延べ4000組以上の家計相談に乗ってきた実績を持ち、ナレソメfinanceではナレソメイトたちの「お金の相談」を受ける山田健介氏と、同社で多くのカップルをサポートする土田昌子氏。最高のパートナーと未来を築くための、本質的な思考法を探ります。
4000組の家計を見てきた、住宅とお金のプロフェッショナル
──まずは、お2人がファイナンシャルプランナー(以下、FP)として活動されるまでのご経歴について、教えてください。
山田:私は新卒で大手ハウスメーカーに入社し、住宅の販売をしていました。家を建てられたお客様は、皆さんとても喜んでくださって、自分の仕事にやりがいを感じていました。
しかし、中には無理なローンの組み方をしてしまい、せっかく手に入れた家を手放さざるを得ない方もいらっしゃいます。そういった方を1人でもなくしたいという思いから、FPの道を目指しました。

その後、FPの資格を取得し、これまで延べ4000組以上のお客様の家計相談を受けてきました。
土田:私は山田と同じハウスメーカーで働いていた時期があり、しかも、小学校・中学校の同級生という縁です。
FPになったのは、自身の結婚や出産がきっかけでした。いざ自分のライフステージが変わると、お金について「これ、知らないと損しちゃうな」という場面が本当に多いことに気づいたんです。

そこで「知らないことで損をする人を1人でも減らしたい」という思いでFPの資格を取得しました。FPとしてのキャリアはまだ3年ほどですが、山田のもとで鍛えられ、今では年間100組ほどのお客様を担当しています。
またナレソメ予備校のナレソメfinanceでは、婚活中や新婚の方々、住宅購入を考え始めたご夫婦まで、幅広くご相談いただいています。
家計において「貯蓄額」より大事なこと
──夫婦が幸せになる「豊かな家計」を作るには、なにが重要なのでしょうか? やはり「貯蓄額」でしょうか?
土田:もちろん貯蓄額も大切ですが、それ以上に重要なのは、お金に対する「意識」や「向き合い方」そのものにあると感じます。
例えば、住宅購入の際に住宅ローンを組もうとした場合、頭金を準備できているかどうかという事実よりも、そもそも「将来のために頭金を準備しよう」という意識や環境があったかどうかが、実はもっと重要なんです。

最近は頭金ゼロでも住宅ローンを組める場合があります。しかし「借りられるからためなくていいや」という考え方だと、その後の返済計画も甘くなりがちで、長期的に見ると家計が厳しくなるリスクがあります。
住宅ローンの例に限らず、まずは自分たちの家計の状況をきちんと把握し、お金と向き合おうという姿勢が、安定した生活につながっていくんです。
山田:土田の話に加えて、もう1つ明確な違いを挙げるとすれば、お金が自動的に「たまる仕組み」を持っているかどうかですね。例えば、企業の福利厚生の1つである「財形貯蓄」はまさにその典型で、自分の意思とは関係なく給料から天引きされ、お金がたまります。
これがあると、意識する前にお金がたまっていく。現在では、NISAやiDeCoが主流になりつつあります。こうした仕組みを、特に若いうちから持っているかどうかは、数年後、数十年後に驚くほど大きな差を生み出します。
「世帯年収1000万円」にも違いがある。共働き夫婦が資産を築きやすい理由
──意識や仕組みが重要だという一方で、世帯年収の高さも重要かと思います。例えば、世帯年収1000万円の家庭って、それなりに余裕があるように見えますが……。
山田:そこが非常に面白いポイントで、同じ世帯年収1000万円でも、内訳によって手元に残るお金、つまり貯蓄力は全く変わってきます。
結論から言うと、「夫の年収1000万円、妻は専業主婦」という世帯より、「夫の年収500万円、妻の年収500万円」という共働き世帯のほうが、手元に残る金額は多い傾向があります。
──それはなぜでしょうか?
山田:理由は2つあります。1つは「税金と社会保険料」です。日本の所得税は累進課税なので、年収が高くなるほど税率も上がります。年収1000万円の人の手取りは、ざっくり700万円台前半くらいになります。
一方で、夫婦が年収500万円ずつ稼いでいる場合、それぞれに適用される税率が低いため、世帯の手取り合計は800万円近くになる。これだけで年間100万円近い差が生まれるわけです。

土田:もう1つの理由は「心理的な側面」ですね。ご主人の年収が1000万円あると、「うちは高収入だから大丈夫」という安心感が生まれ、生活全体の水準が上がりやすい傾向にあります。
山田:年収1000万円になると、周りとの付き合いで少し高いランチに行ったり、後輩にごちそうしたりする機会も増えますしね。
金銭感覚は「家庭での教育」と「スマホ」で作られる
──その「お金に対する意識」は、一体何によって形成されるのでしょうか? ためられる人と使ってしまう人の違いはどこから来るのでしょう。
山田:これは2つの要因が非常に大きいと感じています。
まず1つ目は、「家庭での教育」です。
──家庭での教育、ですか?
山田:日本人はお金に関する教育を学校でほとんど受けません。そのため、多くの人は親の金銭感覚を無意識に引き継ぐ傾向にあります。
例えば、外食といえばいつもファミリーレストランだった家庭で育った人と、記念日には高級なおすし屋さんに連れて行ってもらっていた家庭で育った人では、金銭感覚が全く異なります。
だから、夫婦で金銭感覚が合わないと感じた時、相手を責めるのではなく、「なぜ相手はそう考えるのか?」という背景、つまり育ってきた環境を理解し合うことが非常に重要なんです。
実際に、当社が家計相談を受ける際も、ご夫婦それぞれのご実家のことをお聞きして、金銭感覚の違いを把握することもあります。
そこを理解した上で、「自分たちの家庭ではどういうルールを作っていくか」をプロを交えて話し合う。そうすることで、新たな価値観を築いていけると思います。
──なるほど。もう1つの要因はなんでしょうか?
山田:「スマートフォン」です。
昔は、消費意欲を刺激されるのは、新聞のチラシやテレビCMくらいでした。しかし、現代はスマホを立ち上げれば、SNSなどからインフルエンサーが紹介する魅力的な商品や、きらびやかな生活が絶え間なく流れてきます。

人間の脳は「欲しい」という欲求には勝てないようにできていますから、これだけ刺激を受け続ければ、お金を使ってしまうのはある意味当然なんです。
それに加えて、キャッシュレス決済の普及が拍車をかけています。現金で3万円を払うのには覚悟がいりますが、スマホのボタンを1つ押すだけだと、お金を使っている感覚がどんどん薄れていく。この「刺激の増加」と「支払いの無感覚化」のコンボによって、お金がたまらない人が増えています。
結果として、しっかりと資産形成できる人と、そうでない人の二極化が、以前にも増して進んでいると感じますね。
最強の家計「6つの馬力」で資産を築く
──話を聞いていると、結婚はお金の感覚をアップデートして、家計を見直す絶好の機会かもしれないですね。そのうえで、これから資産を築いていくために、今の時代に最も有効な方法を教えてください。
山田:今の時代、大きな資産を築いているのは、必ずしも年収2000万円を超えるような一部の人たちだけではありません。一般企業にお勤めの方も、資産を築くチャンスがあり、そこで鍵を握るのは「投資」と「副業」です。
しかも、夫婦それぞれがこれらに取り組めると強いですね。
──より詳しく教えてください。
山田:私たちは「6つの馬力(収入源)を持つ」と呼んでいますが、具体的には以下の収入源を持つのが望ましいと考えています。
- 夫の本業収入
- 妻の本業収入
- 夫の副業収入
- 妻の副業収入
- 夫のNISA(投資)
- 妻のNISA(投資)
本業が2つあるだけでも強いですが、お勤め先の会社が認めていれば、ここに副業を加えることができ、収入の柱は4本になります。
さらに、NISAで得た利益は非課税なので、税金を引かれずにまるまる手元に残る。副業も、経費をきちんと計上すれば、本業の給与所得より税金を抑えることが可能です。
この「6つの馬力」を夫婦で協力して回すことができれば、家計はとてつもなく強固になります。実際に、このスタイルを実践して、30代で億単位の資産を持っているご夫婦もいらっしゃるほどです。
結婚は、2人で資産を築いていくチーム作りのスタートでもあります。お互いの年収額面だけで判断するのではなく、こうした「お金への向き合い方」や「家計をチームとして強くしていく視点」を持ってパートナーシップを築いていくことが、これからの時代、何よりも大切になるのではないでしょうか。
一方で、いきなり「6つの馬力」を持つのは難しいかもしれません。そこで、次回は簡単に取り組めるノウハウをお伝えします。婚活中の方にとっても、将来の家計を考えるうえで欠かせないものになるでしょう。
後編へ続く