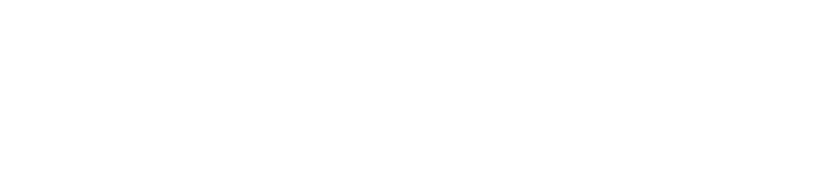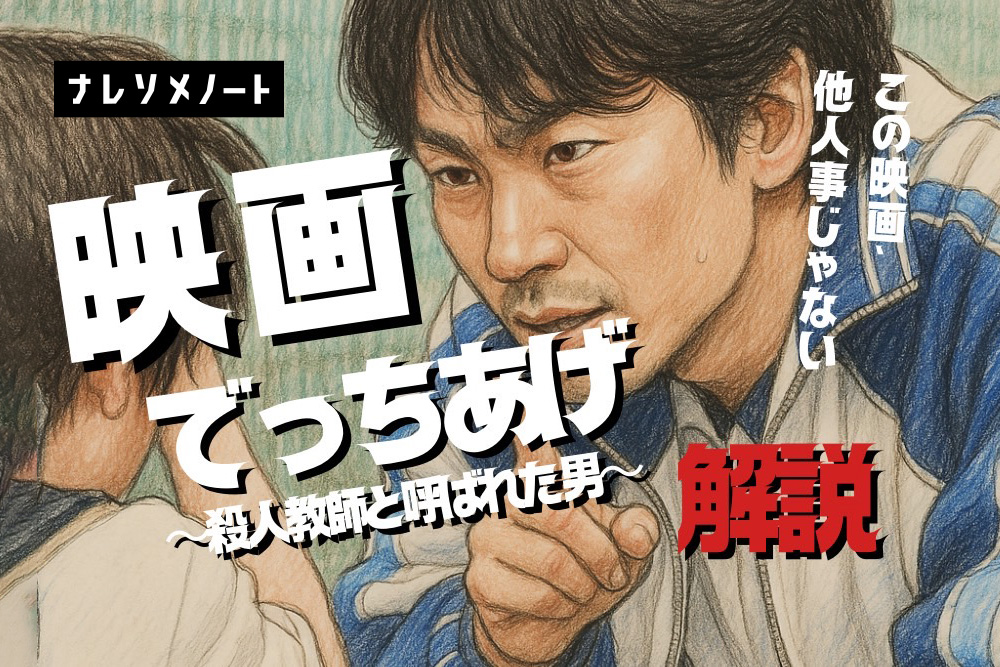貯金ゼロで結婚しても大丈夫。4000組のプロがたどり着いた「たまる仕組み」の作り方と、夫婦の意志を試す『鋼鉄の貯金箱』

婚活で「いいな」と思う相手が見つかったとき、次に考えるべきことは何か。それは、愛情だけでなく「この人と、家庭という会社を一緒に経営していけるだろうか?」という視点かもしれません。
そして、その経営の根幹をなすのが、日々の「お金」の管理体制です。
「会社の資金(共有口座)はどう管理する?」
「経費(生活費)の精算ルールは?」
こうしたルールをどのように設ければいいのか。そこに、相手の価値観やパートナーとしての相性が現れます。
そこで後編では、前編の内容を踏まえて、家計のルールづくりに焦点を当てます。今回も、4000組以上の家計を見てきた実績を持ち、ナレソメ予備校で「ナレソメfinance」を担当する山田健介氏と土田昌子氏に、豊かな家計を築くためのヒントを、引き続き取材しました。
家計改善の第一歩は「ライフプラン」の作成から
──後編では、どうすれば豊かな家計を作れるのか、具体的な方法論に進みたいと思います。「リッチな家庭はリッチ、プアな家庭はプア」で終わっては悲しいので、そうならないための道筋を教えてください。
土田:まず最優先でやっていただきたいのは、夫婦の収入と支出を「透明化」することです。そして、「ライフプラン」を作成し、将来の目標を共有すること。これが全てのスタート地点になります。

ライフプランを作ることで、現在の家計の状況と、このままの生活を続けた場合に将来どうなるかが「可視化」されます。
「お金があるつもりでガンガン使っちゃっている人も、このまま続けるとこうなっちゃうんだよ」というのを、具体的に目で見てわかってもらうと、行動を変える大きなきっかけになります。
「100%変わる計画」を、なぜ作るのか?
──ただ、ライフプランを作っても、その通りに進むことの方が少ないのが人生かと思います。「どうせ変わるのに、作る意味があるのか?」と感じる方もいるかもしれませんが、その点はいかがでしょうか。
土田:おっしゃるとおり、計画通りに進むことはほぼないです。
しかし、「夫婦の価値観をすり合わせるためのツール」として非常に重要なんです。
どの時期に、どんな暮らしをしていたいか。その理想を明確にする中で、夫婦の意見が違うのであれば、意見のすり合わせのために話し合いが必要です。この対話のプロセスにこそ意味があるのです。
例えば、子どもは2人欲しいという計画を立てても、実際には1人かもしれないし、3人になるかもしれない。どんな未来になっても対応できるように、どう転んでも大丈夫なように準備をしておく。そのための第一歩がライフプランなんです。
山田:ライフプランは「夫婦の目的地を合わせる作業」とも言えます。例えば、「僕は海に行きたい、私は山へ行きたい」「僕はアメリカに行きたい、私はヨーロッパに行きたい」となると、どこにも行けませんよね。
お金のことや未来のことになると、こういうすれ違いが起きがちです。

私はこれまで4000組のライフプランを作ってきましたが、1円単位でぴったりになるライフプランは1つもありません。コロナ禍のような誰も予測できないことも起こりますからね。
では、なぜ作るのか。それは、2人が向かう方向を合わせるためです。方向がズレたままでは、夫婦生活が立ち行かなくなってしまいます。
そして、より大事なのは、ライフプランを作り続けることです。理想は、まず結婚、家の購入、子どもの誕生といったライフイベントが起きたときに必ず見直すこと。あとは、特になにもなくても、3年に1回くらいフィナンシャルプランナー(以下、FP)に声をかけていただくのがちょうどいいくらいですね。
その都度FPと一緒に少し先を照らし、軌道修正していく。これがFPの仕事だと思っています。
究極の家計管理術『鋼鉄の貯金箱』とは?
──ライフプランで目標を定めたら、次はいよいよ実践です。我が家では、共同口座を作って毎月定額を入金し、そこから家計費を支払う形をとっています。個人の買い物は、それぞれの手元に残ったお金で、と。こうしたやり方について、何かアドバイスはありますか?
土田:良いやり方だと思います。そのうえで、もう一段階レベルアップさせるなら、生活費の口座とは別に、完全に「ためるため」だけの口座や仕組みをもう1つ作ることをお勧めします。
例えば、「家計としてNISAでいくら積み立てようね」と夫婦で話し合って決めるなど、手を付けずにためていける場所があると、より着実に資産は増えていきます。

山田:家計管理で一番大事なのは、「ストレスなく続けられるやり方」であること。細かい家計簿が苦手な方にそれを強制しても、絶対に続きません。夫婦のどちらかにとってストレスになるやり方はうまくいかないのです。
そして、もう1つ大事なことがあります。それは、「いくらためるか」を夫婦で決めること。これさえできていれば、極論、何にお金を使ってもいいんです。
──「いくらためるか」ですか。
山田:はい。そして、「なぜその金額をためるのか」を夫婦が答えられることが重要です。
「年間100万円ためます」「なぜですか?」と聞かれて、ほとんどの人は答えられません。しかし、ライフプランがあれば、例えば「5年後に300万円の車を買いたいから、月々5万円」「子どもの大学費用として18年後までに800万円必要だから、月々約3.7万円」「老後のために……」というように、目標から逆算してためるべき額が明確に決まります。
そして、その決まった額は、給料が入った瞬間に『鋼鉄の貯金箱』に入れてしまうんです。
── 『鋼鉄の貯金箱』??
山田:えぇ。つまり、自動的に先取りで貯蓄される仕組みのことです。一度そこに入れたお金は、目標の時が来るまで絶対に引き出せないようにする。そうすれば、手元に残ったお金は全て自由に使えるわけですから、ストレスがありません。
この「鋼鉄の貯金箱」の中身は、目的によって使い分けます。老後の資産形成ならNISAや保険、子どもの学費ならNISA、3年後の車の購入資金なら普通預金、というように。もしリスクが取れるなら、投資信託で「うまくいったら高級車、失敗したら大衆車」というような幅を持たせることもできます。

それぞれの目的に対して、一番パフォーマンスが良くてリスクが少ないやり方を、我々プロが一緒に考えて組み合わせていくわけです。
そして、この「鋼鉄の貯金箱」は、物理的なものではなく、「これは未来の自分たちのための、絶対に手を付けてはいけないお金だ」という夫婦の強い意志、つまり精神的なものでもあります。
「これは子どもが大学に行くためのお金だ。本当に今、手をつけるのか?」
「これは自分たちが老後豊かに暮らすためのお金だ。今欲しいもののために、本当に自分たちの未来を壊すのか?」
お金を使いたい誘惑に抗う覚悟。これこそが、「鋼鉄」の意味するところなのです。
老後のための「鋼鉄の貯金箱」としてお勧めなのが、iDeCoです。60歳まで崩せないという特徴をデメリットと受け取る方もいらっしゃいますが、使いたくなっても使えないからこそ、しっかり老後資金をためられる仕組みともいえます。
毎月自動でお金が積み立てられ、運用もされます。しかも掛け金は全額所得控除の対象になりますので、税金のメリットもある。老後の安心を作るために、とても頼もしい制度です。
パートナー選びで重視したい「お金の価値観」
──貯金ゼロからスタートした夫婦でも、そうした仕組みを作れば、豊かな家計を築くことは可能なのでしょうか。
山田:貯金ゼロからでも十分可能です。
また夫婦ともに医師で年収2000万円ずつ、というようなご家庭なら、毎年の稼ぎで全てをまかなえるので、そもそも厳密なプランは必要ないかもしれません。でも、そんな家計はほんの一握りです。
子どもの教育費も、家の購入費も、年間の稼ぎだけでは払えないことがほとんどでしょう。だから「前にためる(資産形成)」か「後ろに伸ばす(ローンや奨学金)」かが必要になる。私たちは、なるべく「前にためる」を増やし、「後ろに伸ばす」を賢く利用するお手伝いをします。
土田:「これまで使い放題だったけれど、1人のお金ではなく家計のお金として2人で考えていくんだ」という意識の切り替えさえできれば、未来は必ず変えられます。その明るい未来をライフプランで可視化してあげると、皆さんのスイッチが入りますね。
── それは心強いですね。それでは最後に、これからパートナーを探す婚活中の方々へ、メッセージをお願いします。
土田:これからの人生を共にするパートナーを探すうえで、お金の価値観は決して外せない重要な要素です。だからこそ、まずはこれまでのご自身のお金との向き合い方に改めて目を向け、振り返ってみてください。
そして、お相手と出会う中で、その方のお金に対する考え方を少しずつ理解していくことが大切です。最終的に、人生で達成したい目標が近い方を見つけられると、幸せな新生活への近道になると思います。
山田:私が伝えたいのは、「お金は目的ではなく、あくまで手段である」ということです。「いくら稼いでいるか」よりも、「そのお金を使って何をしたいか」という価値観が合うことが、長い人生を共にするうえではるかに重要です。
例えば旅行に行くとき、「せっかくだからおいしいものを食べたい」という人もいれば、「工夫して低価格で楽しみたい」という人もいる。どちらが良い悪いではなく、そこの感覚が合うかどうか。家を買い、車を買い、子どもを育て、老後を過ごす。夫婦のあらゆる決断の根幹には、この「何にお金を使いたいか」という価値観があります。
ぜひ、そうした視点でお相手と対話し、関係を深めていっていただければと思います。